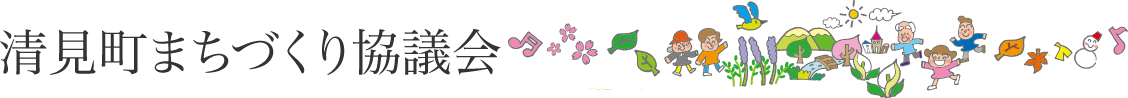【青少年育成委員会より】12月16日(火) わくわく教室 親子クリスマス会
12月16日(火)、三日町ふるさと会館で、わくわく教室の「親子クリスマス会」が行われ、17組の親子が参加しました。
児童センターの「おでかけ隊」のお二人による手遊びやミニ工作、サンタさんのパネルシアターに大型絵本など、親子で楽しめる企画が続き、会場は笑顔であふれていました。
大きな袋を背負ったサンタさんが登場すると、おともだちはとてもうれしそうにプレゼントを受け取りました。
最後は、クリスマスケーキやゼリーを囲みながら、みんなでおしゃべりを楽しみ、和やかな時間となりました。



12月14日(日) “なが~い”太巻きづくり
JAひだ助けあい組織「山びこの会」清見支部は12月14日(日)、活動拠点の「あい・あい館」で、園児から高齢者まで19名が参加する、なが~い太巻き作りの交流会を開きました。
日頃から「あい・あい弁当」などを通して地域に寄り添う同会が企画したもので、飛騨牛や飛騨コシヒカリ、椎茸「飛騨やまっこ」など、清見の恵みをたっぷり使った全長3メートルの太巻きに挑戦しました。
参加者は「せーの」と声を掛け合いながら一気に巻き上げ、見事に完成した瞬間には会場から大きな歓声が上がりました。出来上がった太巻きは、手作りのすまし汁とともにみんなで味わい、会場は終始あたたかな笑顔に包まれました。
世代を超えて協力し合う姿が随所に見られ、地域のつながりを改めて実感できた時間となりました。



【青少年育成委員会より】12月5日(金) 清見町人権タウンミーティング
12月5日(金)、清見中学校体育館で「清見町人権タウンミーティング」を開催しました。
第一部では、飛騨市の勝田なお子さん・萌さん(結萌空間)が講演をし、萌さんが度重なる発作や入院を乗り越えて歩んできた日々を語られました。
プロカメラマン今村さんとの出会いから生まれた写真展や、二十歳を記念して制作された動画も紹介され、命の尊さと前向きに生きる力が伝えられました。
第二部では、小・中学生が「苦手の克服」をテーマに意見交換し、最後に自らの宣言を発表。
締めくくりには生徒による合唱「ほらね。」が披露され、会場は大きな感動に包まれました。
勝田さんからは「やりたいことは声に出そう。諦めないでほしい」との力強い言葉をいただき、子どもたちのまっすぐな姿勢と温かな交流が参加者に勇気を届けた一日となりました。



【生涯学習委員会より】12月4日(木) オリジナルしめ飾りをつくろう
12月4日(木)、きよみ館3階で、伝統文化に触れながらオリジナルのしめ飾りづくりを体験しました。
「毎年楽しみにしています」との声もあり、会場は開始前から和やかな雰囲気に包まれました。
下出日和先生(フラワーハウスしもで)の指導のもと、ごぼう注連縄に松や胡蝶蘭、金色の稲穂を配置。水引は5本を自由に選び、「普段は選ばない色に挑戦しました」といった声も聞かれました。
個性豊かな、世界に一つだけのしめ飾りが完成し、「早く玄関に飾りたい」「家族に見せるのが楽しみです」と喜びの声が上がりました。
新年を迎える準備を整えつつ、創作を楽しむひとときとなりました。



新春マラソンに参加しませんか
第41回 清見新春マラソン
令和8年の元旦、清見で走り初めしませんか?

(当イベントは終了しました)
冬の澄んだ空気の中、みんなで楽しくスタートダッシュ!
参加賞あり!お楽しみの抽選会もありますよ!
日時:令和8年1月1日(元旦)
受付:9:30~10:00/開会式:10:00~/スタート:10:30~
受付場所:清見B&G海洋センター前
コース:松 約1.5km /竹 約2.5km/梅 約3.5km
どなたでも参加OK!家族・友達と気軽にどうぞ♪
※悪天候時は中止になる場合があります
☎お問合せ:清見町まちづくり協議会事務局
0577-77-9516 (月~金 9:00~17:00)
【長寿委員会より】11月20日(木) 第1回 高齢者教室 ~知多半島の歴史に触れる旅~
11月20日(木)、秋晴れの心地よい陽気のなか、愛知県半田市「半田赤レンガ建物」と常滑市「めんたいパークとこなめ」へ出かけました。
ビール製造工場として建てられた半田赤レンガ建物では、明治時代の趣を残す、歴史ある建物や展示を見学。懐かしさと新たな発見に満ちた、充実したひとときとなりました。
続いて訪れためんたいパークとこなめでは、試食や買い物を楽しみながら、笑顔あふれる時間を過ごしました。
最後に訪れたのは、日本最大級の直売所「JAアグリタウンげんきの郷」。新鮮な魚介類や干物、旬のフルーツなど、思い思いに買い物を楽しみました。


【体育委員会より】11月16日(日) 第11回 ソフトミニバレーのつどい
11月16日(日)、B&G海洋センター体育館にて「第11回ソフトミニバレーのつどい」を開催しました。
今回は中高生、ご近所さん、ママ友など多彩な顔ぶれによる8チームが出場。若さあふれるプレーが随所で見られました。
試合はラリーごとに得点が入るラリーポイント制で進められ、各コートで熱戦が繰り広げられました。
白熱したラリーに歓声が響き渡り、名勝負が次々と生まれるたびに会場は一体感に包まれました。
スポーツを通じて地域の絆が広がり、「つどい」の名にふさわしい、楽しく有意義な時間となりました。


【地域より】林野庁長官賞を受賞
二本木生産森林組合(二本木)が、令和7年度全国林業経営推奨行事における今年度の「林野庁長官賞」に選ばれました。
11月6日(木)には、東京都千代田区のイイノホールにて行われた表彰式において、秋篠宮殿下ご臨席のもと、「林野庁長官賞」の表彰状を拝受しました。

【青少年育成員会より】11月5日(水) 清見の教育のこれからを、地域みんなで考える
11月5日(水)、清見支所大会議室にて、「子どもたちの育成を考える会」主催による学習会が開催されました。
少子化が進む中、清見町の教育の将来について地域住民とともに考える貴重な機会となりました。
学習会は二部構成で行われ、第一部では高山市教育委員会事務局 教育総務課長の南元伸一氏より高山市内における義務教育学校の取り組みについて、荘川さくら学園などの事例を交えながら説明していただきました。
第二部では、昨年度まで白川郷学園の校長を務め、現在は高山市教育委員会 学校教育課長の曽出昌宏氏が、白川郷学園などで導入されているブロック制の説明や、地域と連携した教育の実践について紹介されました。
曽出氏は、「人数の多さではなく、どのような教育を行うかが重要である」と述べ、清見町の特色を活かした教育の可能性について提言。
参加者からは、地域の教育についての理解が深まり、より一層の関心が高まったとの声が寄せられました。